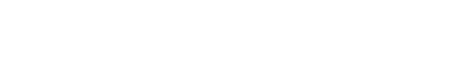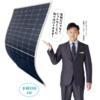ハッピー・ノート.com
Mama's profile/プロフィール

ひらきだ ゆき 【臨床心理士 精神保健福祉士】
記事テーマ
カウンセラー通信:自分らしい楽しいお産と子育てをしよう
初めてのお産・子育てって不安ですよね?でも大丈夫。ママが主体的であれば、赤ちゃんも力を合わせママとお産を頑張ってくれます。初めての母子での共同作業のスタートが主体的であれば、その後の育児もとまどうことはあっても、そのママらしい力が発揮でき、赤ちゃんも自己発揮できます。そのお手伝いを、カウンセラーの視点から楽しく具体的にさせて頂きます!
ほめるって難しい!言葉の引き出しを増やそう/2014年12月
ほめるって難しい!言葉の引き出しを増やそうみんなのコメント :66件
私も、人と接するときに褒めるということがとても難しいと感じることがあります。人を褒めるということがが難しいと感じるようになったのは看護学校に入り実習で受け持ちさんを受け持つようになってからです。それまでは私は人を褒めることに対し、難しいや簡単だという意識がなかったのですが、病院で頑張っている患者さんに対し、どのような声がけが一番適しているのか悩むことがありました。頑張っている患者さんに対し、どの言葉をかけることが適切なのか悩み、結局「頑張ってますね。」や「昨日より上手に歩けてますね。」などしかいうことができませんでした。そのため、101の褒め言葉を少しでも自分の言葉の引き出しに入れ、その人にあった言葉をいえるようにしたいと思いました。
褒められて嬉しくない人はいないと思います。私自身も「髪型似合っているね。」「今日も笑顔が明るいね。」などの声をかけて頂けたら、とても嬉しい気持ちになれます。それは、自分の行動・行為に対して評価してくれていることもそうですが、まず前提として自分のことを見てくれている。と感じるからだと思います。褒めるためには、その人を良く観察し、その人にとってエネルギーが湧く言葉とはどのようなものなのかを考えることが必要だと思います。また、ボキャブラリーを増やすのは難しいと感じました。私はあまり本を読まないので、言葉の引き出しが少ないと思います。そのため、色んな人とたくさんお話をして、言葉の引き出しを増やしていきたいです。褒めるということを難しいと感じ、諦めるのではなく、観察力を養い、ボキャブラリーを増やし、褒め上手になりたいです。
私自身これから先子育てをしていくとしたら、たくさん自分の子どもを褒めていきたいです。実際難しいかもしれませんが、褒めることがエネルギーになりお互いに成長できると思いました。私も幼少期に、母とふたりで夕食の準備をしていく中で「手伝ってくれたから美味しいご飯ができたよ」と言われとても嬉しかったことを覚えています。誰かに言われて嬉しかった言葉や、子どもの成長を見ていく中で感動したことは素直に伝えていきたいし、なにか言葉で伝えることに意味があるのかなと考えました。
褒める、ということは相手を認め安心させる言葉というところがすごく納得できました。私自身何気ないことでもさすがだね、ありがとね、と言われるとすごく誇らしげな気持ちになれたし、頑張ってよかった、と思えたことがたくさんあります。毎日ひとつ認められれば一年で365個も褒めてあげられます。また、同じことを褒められてもうれしいと思います。これが自分の長所なんだと思えるようになると思うので。特にさりげなく言われたときはすごくうれしいと思います。こんなことでも喜んでもらえるのか、と発見にもなるし、言ったほうも、ありがとうっていうと気持ちがいいなと思えたりすると思うので!子どもに対してだけでなく、大人同士でも労りあうと家族全体が温かくなると思いました。
街中で子どもを見かけたとき、どちらかというとお母さんが「静かにしなさい!」とか「危ないよ!」と子どもを怒ったり、注意したりしている場面をよく目にします。また、自分がちいさかった頃、私が友達と遊んでいる時、私のお母さんは私よりも友達のことを褒めていたように思います。そういうことから、自分の子どもを褒めることは実は難しいことなのかなと思いました。
でも、お母さんに「よくできたね!」とか「大丈夫だよ」とか声をかけられたとき、うれしくてもっと頑張りたくなって、心のエネルギーが満たされたことをよく覚えています。子どもにとってはお母さんからの褒め言葉が一番のご褒美なのかなと思いました。どんな声をかけてもらった時が嬉しかったか思い出したり、他の人から教えてもらったりして、子どもの心のエネルギーが満たされる言葉をかけてあげられるお母さんになりたいと思いました。
褒めるというのは意識的に行わないとなんだか恥ずかしかったり、わざわざ言葉で言わなくても伝わっているのではないかと思ってしまうことがあると思います。でも褒められると自分が認められている、自分はここにいて良いのだという安心感がうまれると思うときちんと言葉にして相手に伝えるのが大切だと思いました。褒められる方はもちろん、褒める方も気持ちが良いと思います。お互いに良い気持ちになれる行動をどんどん増やして、心のエネルギーを増やしていきたいなと思いました。
私は褒められるのが好きで、もっと褒められたい!と思って頑張ります。でも、褒められるというよりも、その頑張っていることを認められたいのかもしれないなと思いました。「えらいね」よりも「頑張ってるね」って言われた方が私は心のエネルギーがたまります。でもそれって人によっても違うから、その人その人の心のエネルギーになるような言葉がけができたらいいのかなと思いました。
子供と関わっていく上で 怒ることよりも褒めること 子どもたちにとってプラスになること けなすよりも励まして育てていくことが大切だと思いますし、私もよく耳にします。子どもと関わっていく上で自然と無意識に ダメなこと否定をしてしまっている自分もいました。プラスの言葉を意識して使うことは難しい事でもありますが、とても大切なことだと感じました。これから より子どもと関わっていく場面が増えると思いますが もっともっと意識をして ほめ言葉を使って関わっていけるようにしていきたいと改めて感じました。
私は保育実習に何度か行き、その時の制作活動の時に掛ける褒め言葉に具体性がなく褒めることが難しく感じました。ですが、この記事を読んで「ほめ言葉=認める・安心する言葉=心のエネルギーがわく言葉」と書いてあるのを見て褒め方のパターンを増やすことが何より大切であることがわかりました。先生が大学の講義で実施していたポスターや「親と子を元気にする101の言葉」のポスターを色んな人に書いてもらうことで自分の中の褒める言葉の引き出しが増えたり、こんな褒め方もあったんだという発見をこの記事ですることができ、とてもためになりました。また、自分が褒める時だけでなく子ども自身が友達や家族に対して褒める場面があると思います。そのときにどんな褒め言葉をすることで嬉しいかというのも教えることができるので褒め言葉の引き出しをたくさん持ったいることで周りも幸せにすることができることを学び、幸せな気持ちになりました。
「人は他者を批判するボキャブラリーはたくさんあるのに、他者をほめるボキブラリーは意外と少ない」って確かにそうだと思います。いざ子どもと接するとどんな言葉で褒めたらいいのだろうと悩んでしまいます。直感的に浮かんだ言葉でしか褒められないため、意識的に語彙を増やすという努力をしなければならないのだと改めて思いました。
Comment/この記事にコメントしよう
Archives/ひらきだ ゆきさんの記事一覧
- 「親行動」を考えよう ~私たちは親としてのどうあるべきか~
当たり前のことですが、私たちは今まで受けた教育で「親になるなり方」は学んでいません。 … - 待機児童対策?!育休中に子どもが保育園を退園させられる?!パート3 ~保育士のの視点で捉えるこの問題~
社会問題化している育休退園問題について、今回は保育士の立場からこの問題をどう捉えるのかとい… - 待機児童対策?!育休中に子どもが保育園を退園させられる?!パート2 <~親にとって、自治体にとってのこの問題~>
2015年4月から「子ども子育て支援新制度」が始まり、自治体により親が育児休業(以下、育休… - 待機児童対策?!育休とると、子どもが保育園を退園させられる?!パート1<~子どもにとってのこの問題~>
2015年4月から「子ども子育て支援新制度」が始まり、自治体により親が育児休業(以下、育休… - 保育園は教育をしないのか?パート2
私たちは、どうしても固定観念として、保育園は保育、幼稚園は教育と思い込んでいます。そして、… - 保育園は教育をしないのか?パート1
2015年4月に「子ども子育て支援新制度」がスタートし、保育園は保育、幼稚園は教育、こども… - 簡単!手作り!離乳食タオルエプロン!
離乳食がはじまる頃に、みなさんは市販の離乳食エプロンを買っていますか? … - 下の子の発達が早いのはなぜか?
「下の子の発達は早い」とよく世間ではいいますが、それはなぜでしょうか? … - 子どもを保育園に預けるって悪いこと?!
4月から子どもが保育園に入園するパパ、ママもこの時期多いでしょう。 入園申請の時期や入… - 簡単!無添加!おしりふきのつくり方
みなさんは、子どものおしりふきを買っていますか? ドラッグストアにいくと、様々なおしりふき… - 助産師はどうやってお産を読み取るのか?~ママもパパもお産の流れを理解しよう~
助産師は、医療の視点だけでなく、ママの【体で訴える言葉】を感じ、お産の進みを読み取ります。… - 赤ちゃんのつなぎ服いつまで着させるの?
初めての子育ては、すべてが初めてのことだらけで、授乳・寝かしつけ・抱っこなど色々戸惑うこと… - 子育てでパパたちができる5つのこと
子育ての構造は、パパにとってもママにとっても、負担であり、慣れないものです。 なぜ… - ほめるって難しい!言葉の引き出しを増やそう
「子どもはほめて育てよう」と世間ではよく言いますが、意外と難しいのではないでしょうか?いい… - イライラする!私ってダメな母親?!
赤ちゃんはかわいいですが、いざ子育てが始まると、けっこうイライラしませんか? カウ… - 出産がゴールじゃない~子育て省エネ法のすすめ~
無事にお産が終わり、元気な赤ちゃんと対面すると、喜びや安堵感で、「やっと終わった~」と一安… - カウンセラーが考えるお産10の心得
【人は見通しがたたないと不安】になります。これは誰もがそうです。 「いつ終わるのか… - 二人目のお産は軽いというがなぜ?
よく「二人目のお産は軽い」なんて言いますが、それはなぜでしょうか?その理由を今回改めて考え… - 助産師は字のごとく~ベテラン助産師にインタビュー~
助産師という文字を改めて見ると「お産を助ける人」です。あくまで助産師は助ける・サポートをす… - お産の時一番不安なのは誰?
初めてのお産で、一番不安なのは、ママ・パパ・赤ちゃんの誰でしょうか?もちろん、皆不安です。… - 陣痛=痛い?お産の仕組みを主体的に学ぼう!
初めての出産を前にすると、陣痛への恐怖を誰もが持ちます。どんな痛さなのか? 体験したことが… - きらりと光るパパたちへ:パパはお産のコーディネーター
第1回目の記事で、お産の主役は赤ちゃんとママとお伝えしました。ではパパは脇役なのでしょうか… - 一人で産むの?一緒に産むの?~赤ちゃんからのメッセージに耳を傾けよう~
誰もが、経験したことのない出産は不安です。そんな中、パパや周囲から「頑張って」と言われると… - 発想の転換をしよう。「どんなお産になるのやら」ではなく「どんなお産にしようかな」
初めてのお産って不安ですよね。当たり前ですが、体験したことないし、「鼻からスイカがでるくら…
最新記事
-

ママと赤ちゃんをつなぐ ベビーマッサージ
ベビーマッサージの効果について理解しておくことで、精神面にも効果的な… -
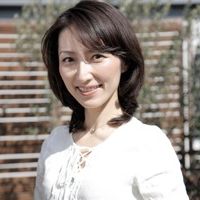
新年、ハーブティーで身体をリセット
新年がスタートして半月、年末年始の食べ過ぎはリセットできていますか?… -

継続するモチベーション
以前、「継続」することの重要性について記事を書きましたが、今回は「継… -

ツリーアレンジでテーブルを華やかに
花空間プロデューサー内田屋薫子が、クリスマスの時期にぴったりのツリー… -

2013年秋冬ファッションの流行色!
9月に入り、朝晩には秋の気配が感じられるようになり、秋冬のおしゃれが… -

産後のエクササイズの前にやっておくと痩せ効果がUPすること
赤ちゃんやこどもと一緒に楽しくエクササイズ! 今回ご紹介するのは、エ… -

根菜を食べて冷え性知らずになろう
だんだん寒くなってくるこの時期。体が冷えると脂肪を蓄えます。根菜を簡… -

子どもの作品を写真で残す!一年に一度の作品整理術
子どもが持ち帰ってくる作品たちを簡単に思い出いっぱいに残す方法…